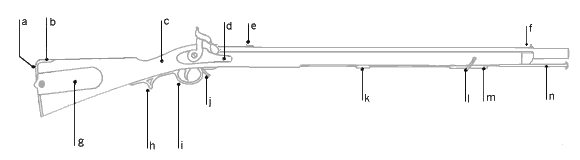

この時代の軍用銃の主流は、前装滑腔式マスケット銃であった。前装施線銃(=ライフル小銃)や、後装式も、すでに開発されていたが、製造コストの高さや装填し難さから主流とはならず、狙撃兵の武器として用いられる程度であった。
この時代の小銃ほとんどは単発前装式であり、フリントロック式(火打ち石式)と呼ばれる点火方式が一般的であった。多銃身の連発前装式銃もかなり古くから存在していたのだが、たいていは高価なため、それらは狩猟・護身用、もしくは観賞用の武器でしかなかった。
この方式は、1610年頃には登場して、パーカッションロック式(管打ち式)と後装式が組み合わさって軍用小銃に大きな革新がもたらされる1850年代(明治維新前後)まで、長々と世界の標準的主力銃の地位にあった。産業革命が技術全般の革新に影響を与え、マスケット銃を主役から追いやるが、それまで、兵士達はあまり改良を加えられることなかったマスケット銃という兵器を与えられ、戦場に送られていた。以下では①〜⑧のポイントにわけてマスケット銃の特徴などを説明する。

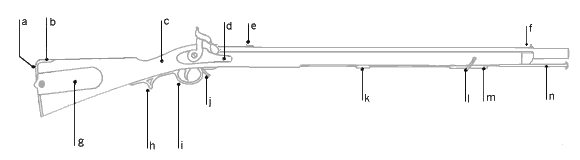
| a | 床尾板 | b | 床尾板の舌状部 | c | 銃床の握り | d | 発射装置 | e | 照門 | f | 照星 |
| h | グリップ | i | 用心鉄 | j,l | 叉銃環 | k,m | 込め矢筒 | n | 込め矢 | g | パッチボックス |
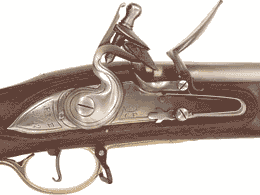 |
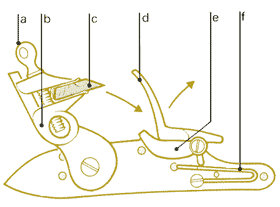 |
| a | つめねじ | b | コック | c | フリント (火打ち石) | d | 当り金 | e | 火皿 | f | 当り金用 スプリング |
 マスケット銃は、火打ち石の摩耗や、湿った火薬、装填の不手際などによってかなり割合で不発が起こった。一般に晴れた日の乾いた状態で15%、湿っていると30%もの高い確率で不発が起こったと言う。 英軍の1834年の実験によると、正確な不発率は理想的な条件下ですら 2/13 %であったという結果がでている。
マスケット銃は、火打ち石の摩耗や、湿った火薬、装填の不手際などによってかなり割合で不発が起こった。一般に晴れた日の乾いた状態で15%、湿っていると30%もの高い確率で不発が起こったと言う。 英軍の1834年の実験によると、正確な不発率は理想的な条件下ですら 2/13 %であったという結果がでている。 これは弾の威力をほとんど消滅させ、弾丸は目標の遥か手前に力なく落ち、有効弾とはならなかった。このような射撃は特に見苦しいこともあって、各国の歩兵隊では訓練で厳しくしつけていたが、前述の火薬の湿りなどの影響もあり、すべての装薬が正しく燃焼しないことは、戦場ではよくおきた。この白煙とともに吹き出す火薬粉は、兵士達の視界を一時的に奪うだけでなく、慢性的な目の炎症の原因にもなった。
これは弾の威力をほとんど消滅させ、弾丸は目標の遥か手前に力なく落ち、有効弾とはならなかった。このような射撃は特に見苦しいこともあって、各国の歩兵隊では訓練で厳しくしつけていたが、前述の火薬の湿りなどの影響もあり、すべての装薬が正しく燃焼しないことは、戦場ではよくおきた。この白煙とともに吹き出す火薬粉は、兵士達の視界を一時的に奪うだけでなく、慢性的な目の炎症の原因にもなった。 ここでいうカートリッジというのは、現代の薬莢と違って雷管を含まず、単に鉛球と計量済みの一回分の火薬が、油紙、蝋または獣脂を塗った紙、中古紙(しばしば本のページの再利用など)で包まれただけのものである。
ここでいうカートリッジというのは、現代の薬莢と違って雷管を含まず、単に鉛球と計量済みの一回分の火薬が、油紙、蝋または獣脂を塗った紙、中古紙(しばしば本のページの再利用など)で包まれただけのものである。  |
 |
 |
| 注:図は”早合”ではなく、欧州の薬包 |
 |
| ケース入り弾薬箱 (腰に付ける) |
 当時のイギリス軍の場合、銃身が11番口径(0.76インチ)で弾丸が14番口径(0.71インチ)というのが標準で、この銃身の内径と弾の直径との差、0.05インチ(約1.27mm)が”遊隙(windage)”であった。
当時のイギリス軍の場合、銃身が11番口径(0.76インチ)で弾丸が14番口径(0.71インチ)というのが標準で、この銃身の内径と弾の直径との差、0.05インチ(約1.27mm)が”遊隙(windage)”であった。  複雑な操作手順(細かく見ると17ステップほどある)にもかかわらず、エキスパート達の主張するところによれば、良く訓練された兵士は毎分5発は撃つことができるとのことで、理論上は6発も可能ともいうが、当時の戦場では通常の場合は毎分2~3発であったと考えられている。
複雑な操作手順(細かく見ると17ステップほどある)にもかかわらず、エキスパート達の主張するところによれば、良く訓練された兵士は毎分5発は撃つことができるとのことで、理論上は6発も可能ともいうが、当時の戦場では通常の場合は毎分2~3発であったと考えられている。 また速射はしばしば事故を招いた。暴発は言うに及ばないが、他で多いのが込め矢を銃身に差したまま忘れて発砲することで、込め矢は弾丸と一緒に高速で飛び出るが、この棒は次の装填に必要である。戦場ではシャレにならない。早いスピードでの射撃と装填動作を持続することは、人間である以上、疲労が邪魔をして不可能である。また前述の銃身の加熱の問題があるので、一般的には長時間の銃撃戦でも、適度な間隔をあけて射撃するのが普通で、望ましいとされていた。
また速射はしばしば事故を招いた。暴発は言うに及ばないが、他で多いのが込め矢を銃身に差したまま忘れて発砲することで、込め矢は弾丸と一緒に高速で飛び出るが、この棒は次の装填に必要である。戦場ではシャレにならない。早いスピードでの射撃と装填動作を持続することは、人間である以上、疲労が邪魔をして不可能である。また前述の銃身の加熱の問題があるので、一般的には長時間の銃撃戦でも、適度な間隔をあけて射撃するのが普通で、望ましいとされていた。 | 表Ⅰ W.ミュラーの実験結果(1811年) 「Elements of the Science of War」 より 銃 : ”ブラウン・ベス”(英) 標的 : 騎兵サイズ |
表Ⅱ ピカードの実験結果 「La campagne de 1800 en Allemagne」より 銃 : ”シャルルヴィル”(仏) 標的 : 1.75m × 3m |
表Ⅲ プロシア軍の実験結果 銃 : 1809年型”ニュー”(普) 標的 : 1.83m × 30.48m (6 ft. × 100 ft.) |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
(備考: Yard = 0.9144m, 1yd. = 3ft. ) |
(備考: 歩[pace] = 2.5 ft.) |
| 銃の種類 | 距離 (標的は射手と同じ歩兵中隊サイズ) | |||
| 75 m | 150m | 225m | 300m | |
| Altpreußischen Gewehr M 1782 | 46% (92/200) | 32% (64/200) | 32% (64/200) | 21% (42/200) |
| 同 (三角銃尾を付けて) | 75% (150/200) | 50% (100/200) | 34% (68/200) | 21% (42/200) |
| Nothardt Gewehr M 1805 | 73% (145/200) | 49% (97/200) | 28% (56/200) | 34% (67/200) |
| Neupreußischen Gewehr M 1809 | 77% (153/200) | 57% (113/200) | 35% (70/200) | 21% (42/200) |
| Charleville | 76% (151/200) | 50% (99/200) | 27% (53/200) | 28% (55/200) |
| Brown Bess | 47% (94/200) | 58% (116/200) | 38% (75/200) | 28% (55/200) |
| Russian musket M1798 | 52% (104/200) | 37% (74/200) | 26% (51/200) | 29% (58/200) |
 小銃が性能通りに機能し、たとえ弾が予想の数だけ命中していたとしてもそれが有効な打撃となり、敵を死傷させることができるかは別の問題である。軍服の端やコート、帽子に穴を開けるだけのことはよくあったし、跳弾や装薬を減らしたりして威力を失った弾丸は、しばしば軍服を貫通することすらできずに、兵士を失神させるだけにとどめることがあったことが当時の証言からわかっているからだ。また戦場では多くの障害があり、実験のような環境は現実離れしていたから、実戦での結果と照らし合わせる必要があり、⑦で見たように、実験の標的は非常に大きいものであったので、銃(とその運用方法)の有効性は別に計測する必要があった。
小銃が性能通りに機能し、たとえ弾が予想の数だけ命中していたとしてもそれが有効な打撃となり、敵を死傷させることができるかは別の問題である。軍服の端やコート、帽子に穴を開けるだけのことはよくあったし、跳弾や装薬を減らしたりして威力を失った弾丸は、しばしば軍服を貫通することすらできずに、兵士を失神させるだけにとどめることがあったことが当時の証言からわかっているからだ。また戦場では多くの障害があり、実験のような環境は現実離れしていたから、実戦での結果と照らし合わせる必要があり、⑦で見たように、実験の標的は非常に大きいものであったので、銃(とその運用方法)の有効性は別に計測する必要があった。| Hanger | Roquerol | Henegan | Muller | Guibert | Gassendi |
| 0.5% | 0.2 ~ 0.5% | 0.2% | 4% | 0.2% | 0.033% |
| Piobert | Decker | Jackson | Napier | Hughes | Anonymous |
| 0.01 ~ 0.03% | 0.01% | 0.5% | 0.33% | 3 ~ 5% | 0.1% |
 しかしこの実験と実戦における40倍近い差にはいくつかの理由が考えられた。
しかしこの実験と実戦における40倍近い差にはいくつかの理由が考えられた。 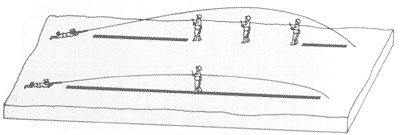 歩兵士官たちは、効果的な射撃にするためにできるだけ敵をひきつけてから一斉射撃を開始したが、実際には有効射程のすこし内側(80〜160ヤード)というのは、弾丸がもっとも高く上がる距離であった。弾道の弧を知らずに、至近距離で水平の照準線のまま発砲すると、弾丸は狙いよりも上方に飛んでいって当たらなかった。
こういったことを将兵は往々として知らず、高低差(射手と標的の間に高低差がある場合は、初速の遅い小銃で射撃するのはさらに困難になる)や距離を考慮に入れた射撃法の知識が不足しており、訓練も十分ではなかった。敵兵を目の前にして怯むと、本能的に恐れから狙いは上に向きがちで、発砲のときの衝撃と、銃口を上に向ける反動(マズルジャンプ)も働いて、弾丸ははるかかなたに発射されることが多かったのである。
歩兵士官たちは、効果的な射撃にするためにできるだけ敵をひきつけてから一斉射撃を開始したが、実際には有効射程のすこし内側(80〜160ヤード)というのは、弾丸がもっとも高く上がる距離であった。弾道の弧を知らずに、至近距離で水平の照準線のまま発砲すると、弾丸は狙いよりも上方に飛んでいって当たらなかった。
こういったことを将兵は往々として知らず、高低差(射手と標的の間に高低差がある場合は、初速の遅い小銃で射撃するのはさらに困難になる)や距離を考慮に入れた射撃法の知識が不足しており、訓練も十分ではなかった。敵兵を目の前にして怯むと、本能的に恐れから狙いは上に向きがちで、発砲のときの衝撃と、銃口を上に向ける反動(マズルジャンプ)も働いて、弾丸ははるかかなたに発射されることが多かったのである。 そして第三に、当時の鉛の弾丸が粗製で形状にバラツキがあったことである。そういう弾丸を楽に装填するためには弾丸と口径との差、”遊隙”にかなりの余裕をもたせる必要があったが、これらは共に精度を落とす要因となったのである。弾丸の変形、形や重さの不均等は、変化球となって弾道を狂わせる。余計な遊隙は弾丸がガス圧で銃口から排出されるときの方向にブレを生じさせ、初速も減じるので、集弾率を悪くした。1740年代の実験で、すでに遊隙のゆるいマスケット銃と狭いものとでは、集弾のサークルは2倍程度差があったことがわかっていた。銃を固定した実験でも100ヤード先では弾の分布は120センチの円に達したから、射撃実験ではかなり大きな標的を目標としているのはとは違って、実戦でこれほどの偏差があれば結果に大きく影響したということは容易に想像できる。
そして第三に、当時の鉛の弾丸が粗製で形状にバラツキがあったことである。そういう弾丸を楽に装填するためには弾丸と口径との差、”遊隙”にかなりの余裕をもたせる必要があったが、これらは共に精度を落とす要因となったのである。弾丸の変形、形や重さの不均等は、変化球となって弾道を狂わせる。余計な遊隙は弾丸がガス圧で銃口から排出されるときの方向にブレを生じさせ、初速も減じるので、集弾率を悪くした。1740年代の実験で、すでに遊隙のゆるいマスケット銃と狭いものとでは、集弾のサークルは2倍程度差があったことがわかっていた。銃を固定した実験でも100ヤード先では弾の分布は120センチの円に達したから、射撃実験ではかなり大きな標的を目標としているのはとは違って、実戦でこれほどの偏差があれば結果に大きく影響したということは容易に想像できる。 しかるに、19世紀において、ほとんど訓練を受けた事も 無い兵士たちが、肉薄した戦闘に臨まなければならなかったとしたら、果して彼らは容易く人を撃ち殺すことができただろうか?
しかるに、19世紀において、ほとんど訓練を受けた事も 無い兵士たちが、肉薄した戦闘に臨まなければならなかったとしたら、果して彼らは容易く人を撃ち殺すことができただろうか? 結局、それは兵器としての性能のみによるものではなく、戦術と訓練、産業技術による結果だったのである。これらがすべて改善されるのには20世紀まで待たなければならなかったから、戦場では銃剣突撃による心理的効果に期待するところが多いという状態が続いていたというわけであり、敵を殺すことよりも敵の士気を打ち崩すことに重点が置かれていたわけである。
結局、それは兵器としての性能のみによるものではなく、戦術と訓練、産業技術による結果だったのである。これらがすべて改善されるのには20世紀まで待たなければならなかったから、戦場では銃剣突撃による心理的効果に期待するところが多いという状態が続いていたというわけであり、敵を殺すことよりも敵の士気を打ち崩すことに重点が置かれていたわけである。