 フランスのスタンダード小銃・”シャルルヴィル”
フランスのスタンダード小銃・”シャルルヴィル” ここではフランス、イギリス、プロシアら、ヨーロッパの主要な軍事大国であった列強国の制式小銃を、ナポレオン戦争の時期の兵器を中心に、個別に紹介する。いくつかの武器は、革命のずっと以前からほとんど変更無く使われていものがあるが、それらも新しいバージョンで記している。ただそれはその年に開発されたというわけではなく、単にモデル年号というだけであるので、誤解しないように。
ここではフランス、イギリス、プロシアら、ヨーロッパの主要な軍事大国であった列強国の制式小銃を、ナポレオン戦争の時期の兵器を中心に、個別に紹介する。いくつかの武器は、革命のずっと以前からほとんど変更無く使われていものがあるが、それらも新しいバージョンで記している。ただそれはその年に開発されたというわけではなく、単にモデル年号というだけであるので、誤解しないように。

| (備考:上図①②③は同縮尺) | 銃身 | 全長 | 口径 | 重量 | 弾丸 | 銃剣 |
| ① Ⅸ年型/ⅩⅢ年型・シャルルヴィル | 113.7cm | 151.5cm | 17.5mm | 4.375kg | 20.6g (22番) | 40cm |
| ② Ⅸ年型/ⅩⅢ年型・ドラグーン・マスケット | 103cm | 141.7cm | - | 4.275kg | - | - |
| ③ Ⅸ年型/ⅩⅢ年型・カービン銃(滑腔式) | 85cm | 115cm | - | - | - | 48.7cm |
| ④ ⅩⅢ年型・騎兵ピストル | 20.7cm | 35.2cm | 17.1mm | 1.269kg | 14.6g (31番) | n/a |
 フランスのスタンダード小銃・”シャルルヴィル”
フランスのスタンダード小銃・”シャルルヴィル” |
 |
 |
 |

| (備考:番号は上から;①②③は同縮尺) | 銃身 | 全長 | 口径 | 重量 | 弾丸 | 銃剣 |
| ⓐブラウン・ベス (Long Land Pattern: 1730) |
116.8cm [ 46in. ] |
158.8cm [ 62.5in. ] |
19.3mm [ 0.76in. ] |
4.082kg [ 9.0lbs ] |
- | |
| ① ブラウン・ベス (Short Land Pattern: 1768) |
106.7cm [ 42in. ] |
147.3cm [ 58in. ] |
19.8mm [ 0.77in. ] |
4.626kg [ 10.2lbs ] |
32.4g (14番) |
43.2cm [ 17in. ] |
| ② ブラウン・ベス ( India Pattern) | 99.1cm [ 39in. ] |
139.7cm [ 55in. ] |
19.1mm [ 0.75in. ] |
4.422kg [ 9.75lbs ] |
- | - |
| ③ ブラウン・ベス (New Land Pattern) | 106.7cm [ 42in. ] |
149.8cm [ 59in. ] |
19.1mm [ 0.75in. ] |
4.706kg [ 10 3/8lbs ] |
- | - |
| ④ 1796年型・カービン銃 (Elliott Pattern) | 66.04cm | 105.41cm | 19mm | 3.632kg | 41.3g (11番) |
38.1cm |
| ⑤ 1796年型・軽騎兵ピストル | 22.86cm | 38.1cm | 15.7mm | 1.134kg | ? | n/a |
 イギリスのスタンダード小銃・”ブラウン ベス”
イギリスのスタンダード小銃・”ブラウン ベス” |
 |
 |
 |

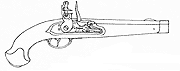 ⑤
⑤
| (イラストは同縮尺ではありません) |
銃身 | 全長 | 口径 | 重量 | 弾丸 | 銃剣 |
| ⓐ Altpreußischen-Gewehr M1782 | 105.3 cm | 146.5 cm | 18.6 mm | ? | ? | 37 cm |
| ① フュージリア-マスケット (1796年改修) | 104cm | 145cm | 18mm | ? | ? | ? |
| ⓑ Nothardt-Gewehr M1801 | 104cm | 145cm | 15.69mm | 5kg | ? | ? |
| ② ニュープロシア-マスケット (Neupreußischen-Gewehr M1809 ) |
104.5cm [41 1/8in.] |
143.5cm [56 1/2in.] |
19.05mm [0.75in.] |
4kg [8.82lbs] |
? | 46.2cm [18 1/2in.] |
| ③ 1787年型・ユサール用滑腔式カービン銃 |
||||||
| ④ 1789年型・騎兵ピス トル |
27.94cm |
? |
17mm |
? |
? |
n/a |
| ⑤ 1813年型・騎兵ピストル | 41.5cm | 24.1cm | 16.2mm | 1.28kg |
 プロシアのスタンダード小銃
プロシアのスタンダード小銃 |
 |
 |
 |