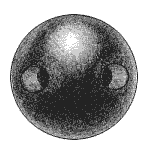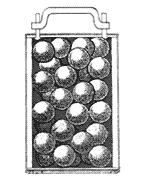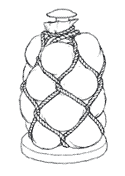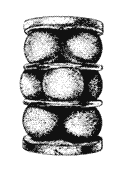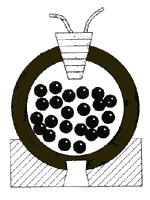ナポレオン戦争の頃、砲弾には基本的に5つのタイプがあった。すなわち球形弾(砲丸)、榴弾、焼夷弾、散弾、榴散弾(シュラプネル)の5種類である。さらに散弾には、内部に複数の大型の子砲弾が込められているものと、多数のより小型の子砲弾が込められているもの、ケースに内容物が収められた缶状の形態をしているものと、子砲弾がむき出しになっているブドウ状の形態のものとがあった。当時、もっとも多く使われたのは球形弾で、使用された砲弾全体の70%~80%以上に及んだ。砲弾の大きさや重さは最小1ポンドから最大68ポンドまで様々で、使用される大砲によって変わってくる。ナポレオン戦争の頃には規格の統一化が進み、雑多な砲弾に砲兵が悩まされるということは減ってきたが、度量衡の不統一から、同じ重量の砲弾であっても実際には製造場所によってかなりの違いがあった。
ナポレオン戦争の頃、砲弾には基本的に5つのタイプがあった。すなわち球形弾(砲丸)、榴弾、焼夷弾、散弾、榴散弾(シュラプネル)の5種類である。さらに散弾には、内部に複数の大型の子砲弾が込められているものと、多数のより小型の子砲弾が込められているもの、ケースに内容物が収められた缶状の形態をしているものと、子砲弾がむき出しになっているブドウ状の形態のものとがあった。当時、もっとも多く使われたのは球形弾で、使用された砲弾全体の70%~80%以上に及んだ。砲弾の大きさや重さは最小1ポンドから最大68ポンドまで様々で、使用される大砲によって変わってくる。ナポレオン戦争の頃には規格の統一化が進み、雑多な砲弾に砲兵が悩まされるということは減ってきたが、度量衡の不統一から、同じ重量の砲弾であっても実際には製造場所によってかなりの違いがあった。
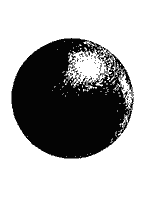
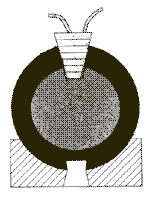
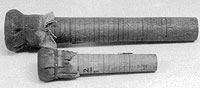 しかしこういった方法のために、爆発時間を正確に調整するのはかなりの経験を要した。榴弾は中空で爆発するときが最も効果的であったが、タイミングが合わずに地上に落ちて爆発することが多く、落ちてもすぐに爆発しないようだと、敵が火を消して爆発を未然に防がれてしまうこともあり、雨天で地面がぬかるんでいるようだと、落下で泥にめり込み、爆発の威力が吸収されて無力されることもしばしばだった。
しかしこういった方法のために、爆発時間を正確に調整するのはかなりの経験を要した。榴弾は中空で爆発するときが最も効果的であったが、タイミングが合わずに地上に落ちて爆発することが多く、落ちてもすぐに爆発しないようだと、敵が火を消して爆発を未然に防がれてしまうこともあり、雨天で地面がぬかるんでいるようだと、落下で泥にめり込み、爆発の威力が吸収されて無力されることもしばしばだった。